経済思想史
| 経済学 |
|---|
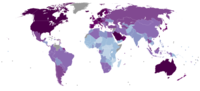 |
| 理論 |
| ミクロ経済学 マクロ経済学 数理経済学 |
| 実証 |
| 計量経済学 実験経済学 経済史 |
| 応用 |
|
公共 医療 環境 天然資源 農業 開発 国際 都市 空間 地域 地理 労働 教育 人口 人事 産業 法 文化 金融 行動 |
| 一覧 |
|
経済学者 学術雑誌 重要書籍 カテゴリ 索引 概要 |
| 経済 |
|
|
| 科学史 |
|---|
| カテゴリ |
経済思想史(けいざいしそうし、英: history of economic thought)は、思想史の一種である。経済思想(経済現象をとらえる基盤となる思想)そのものや、その歴史を研究する学問の分野を指す。日本においては経済学史(history of economics)という名称も使われる[注 1]。
概要
経済学は人間生活と結びついたことを研究するため、悪くいえば「俗世間の真中にいる学問」でもある[1]。やや誇張的に表現すれば、「どうすれば富裕層になれるのか、逆にどういうときに貧困に陥るのか」や「どのような企業が効率的で、どのような企業が非効率的か」などを扱うので[注 2]、金融、貿易、労働、財政、社会保障などの政策が絡むから、官庁で働く人も関与してくるし、マスメディア関係者も動向を世に報告する[3]。とはいえ、いずれも役割が大きく異なるため、こうした人々がどのような仕事において役割を果たしているかに注意を払う必要がある[3]。
要するに経済思想史を語るとなると、結局は「どういう人々がどういう成果を世に問い、それがどう評価されたか」に帰着するが、現状を分析して自説を作り、かつ公表するときは、「背後にある経済事情がどうであるかを知っているか」が前提となる[3]。
主要な経済思想
以下は経済思想史で取り上げられる主なトピックをほぼ年代順に並べたもの。詳しくは、それぞれの項目を参照。
- 古典派以前の西欧
- 古典派以降の西欧
- 古典派経済学
- イギリス古典学派
- ドイツ歴史学派
- マルクス経済学
- 限界効用学派
- アメリカ制度学派 - 制度派経済学
- ケインズ経済学 - ニュー・ケインジアン
- 新古典派経済学
- 新しい古典派
- 合理的期待形成学派
- 進化経済学
- ゲーム理論
- 非ヨーロッパ圏
- 近代以降
脚注
注釈
- ^ 瀧本誠一 (1929)、大矢真一 (1980)、杉原四郎 (1992)など多数。また、学術研究団体に経済学史学会がある。
- ^ 中村隆之は「良い金儲けを促進し、悪い金儲けを抑制することで、社会を豊かにしようとする学問が経済学である」と定義し、経済学の歴史を「様々な悪い金儲けが力を持ってしまうたびに、それに対抗する手段を講じていくという形で展開されてきた」とする[2]。
出典
- ^ 橘木俊詔 (2019), p. Ⅲ.
- ^ 中村隆之 (2018), p. 4.
- ^ a b c 橘木俊詔 (2019), p. Ⅳ.
参考文献
- 中村隆之『はじめての経済思想史:アダム・スミスから現代まで』講談社〈講談社現代新書〉、2018年6月。ISBN 978-4-06-512227-3。
- 橘木俊詔『日本の経済学史』法律文化社、2019年10月。ISBN 978-4-589-04035-0。
- 杉原四郎『日本の経済学史』関西大学出版部、1992年10月。ISBN 4-87354-148-4。
- 大矢真一『日本経済学史の旅:江戸時代の経済学者たち』恒和出版〈恒和選書〉、1980年6月。
- 住谷悦治『日本経済学史の一齣』大畑書店、1934年6月。
- 住谷悦治『日本経済学史の一齣:社會政策学会を中心として』日本評論社、1948年5月。
- 住谷悦治『日本経済学史』(増訂版)ミネルヴァ書房、1967年10月(原著1958年1月)。
- 瀧本誠一『日本経済学史』春秋社〈春秋文庫〉、1929年5月。
関連文献
- 八木紀一郎『経済学入門シリーズ:経済思想』第2版、日本経済新聞社〈日経文庫〉、2011年5月。ISBN 978-4-532-11243-1
- 中山智香子『経済学の堕落を撃つ:「自由」VS「正義」の経済思想史』講談社〈講談社現代新書〉、2020年11月。ISBN 978-4-06-521953-9
- 松原隆一郎『金融危機はなぜ起きたか?:経済思想史からの眺望』新書館、2009年8月。ISBN 978-4-403-23114-8